Contents
保育園での褒め言葉:子どものやる気と自信を引き出す声かけの工夫
保育園で「子どもを褒める言葉」はたくさんありますが、褒めることが本当に効果的なのかと悩む保育士も多いのではないでしょうか。
私自身、保育実習中に先輩保育士の指導を見て、「あんなに叱ったり、厳しくできない」と自信を失ってしまったことがありました。
実際に保育士として働き始めてからも、どのように子どもに声をかけるべきか試行錯誤する日々が続きました。叱ること、褒めること、そしてそのバランスに悩みながらも、「これなら子どもに伝わる」と手応えを感じられるようになったのは、数々の経験を重ねたからこそです。
この記事では、「保育園で子どもを褒める言葉」について、どんな言葉が効果的なのか、そしてその使い方や注意点を実例を交えてお伝えします。
子どもを褒めることの効果と落とし穴
子ども目線で考えると、叱られるより褒められたほうが嬉しいのは当然のことです。
実際に、友だちが褒められる様子を見て、「自分も真似しよう」と考える子は少なくありません。
しかし、褒めることにはメリットだけでなく、注意すべきポイントもあります。
私が年中クラスを担当した際、「先生見て! すごい?」「上手?」と確認してくる子が多いことに気づきました。最初は「すごいね!」「上手!」と返していましたが、やがて「褒めてもらうために行動しているのでは?」と違和感を覚えるように。
このように“褒められること”が目的化すると、自発的な行動が減り、承認を求め続ける状態になってしまうこともあるのです。
また、叱られた経験が少ない子は、注意されたことそのものより「叱られた」という事実にショックを受けて萎縮してしまう場合もあります。
保育士が実践する声かけの工夫:「共感」と「勇気づけ」
子どもが頑張っている姿を見たとき、保育士は「褒めたい」「認めたい」と感じます。とはいえ、言葉の選び方には細やかな配慮が必要です。
最近注目されているのが「アドラー心理学」における“共感”や“勇気づけ”の考え方です。
実例①:一人でできたことを認める
0歳児クラスで、ズボンを自分で脱げるようになったAちゃん。
最初は泣いていたAちゃんが、ある日、裏返ったズボンを私に自慢げに見せてきました。
「一人で脱げたの?嬉しいね!先生も嬉しいな」と声をかけたところ、Aちゃんは満面の笑み。
それ以降、自ら進んで着替えるようになりました。
“すごいね!”と褒めるのではなく、「できて嬉しいね」と共感する言葉を使うことで、子どもの達成感を育てることができます。
実例②:お手伝いをしてくれたとき
年中クラスのYちゃんは、いたずら好きで友達とのトラブルが多かった子でした。
気分転換になればと思い、園長先生の忘れ物を届けてもらうようお願いしたところ、嬉しそうに引き受けてくれました。
園長先生から「ありがとう、探していたんだよ」と声をかけられ、クラスに戻ってきたYちゃんには私からも「助かったよ、ありがとう」と伝えました。
照れくさそうにしながらも、Yちゃんの顔は嬉しさでいっぱい。
「ありがとう」「助かった」などの言葉は“勇気づけ”の言葉です。子どもは「自分が役に立った」と実感し、自己肯定感が高まります。
褒め言葉の選び方と伝え方のポイント
- 「すごい」「えらい」だけで終わらない:行動の“結果”よりも“プロセス”や“気持ち”に目を向けて言葉をかけましょう。
- 共感を含める:「○○してくれてうれしい」「できて嬉しいね」など、保育士と子どもが気持ちを共有できる言葉が効果的です。
- 自己肯定感を育てる:「ありがとう」「助かったよ」「頑張ってたね」など、子ども自身が「価値ある存在」だと感じられる声かけを心がけましょう。
まとめ:褒めるだけでなく“共感”と“勇気づけ”を大切に
子どもを褒めることは、保育において大切な要素ですが、何より大切なのはバランスです。
「褒める」「叱る」だけでなく、子どもに寄り添い、気持ちに共感し、自信を育てる“勇気づけ”の言葉を意識することで、子どもの行動や言葉は自然と変化していきます。
そして、それは保育士自身の気持ちにも余裕をもたらし、よりよい関係づくりにつながります。
褒め方に悩んでいる保育士の方へ──“共感”と“勇気づけ”を意識した声かけで、子どもとの関係がもっと豊かになることを、ぜひ実感してみてください。
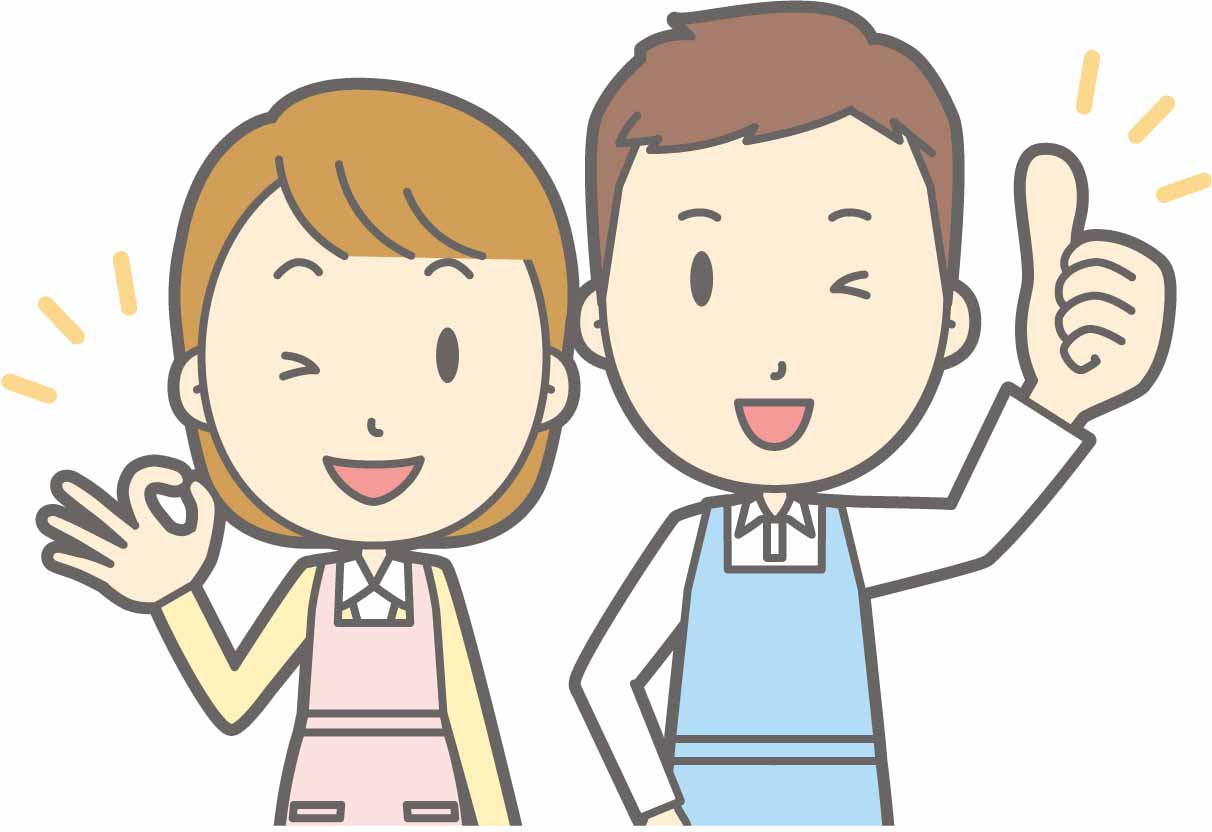


コメント