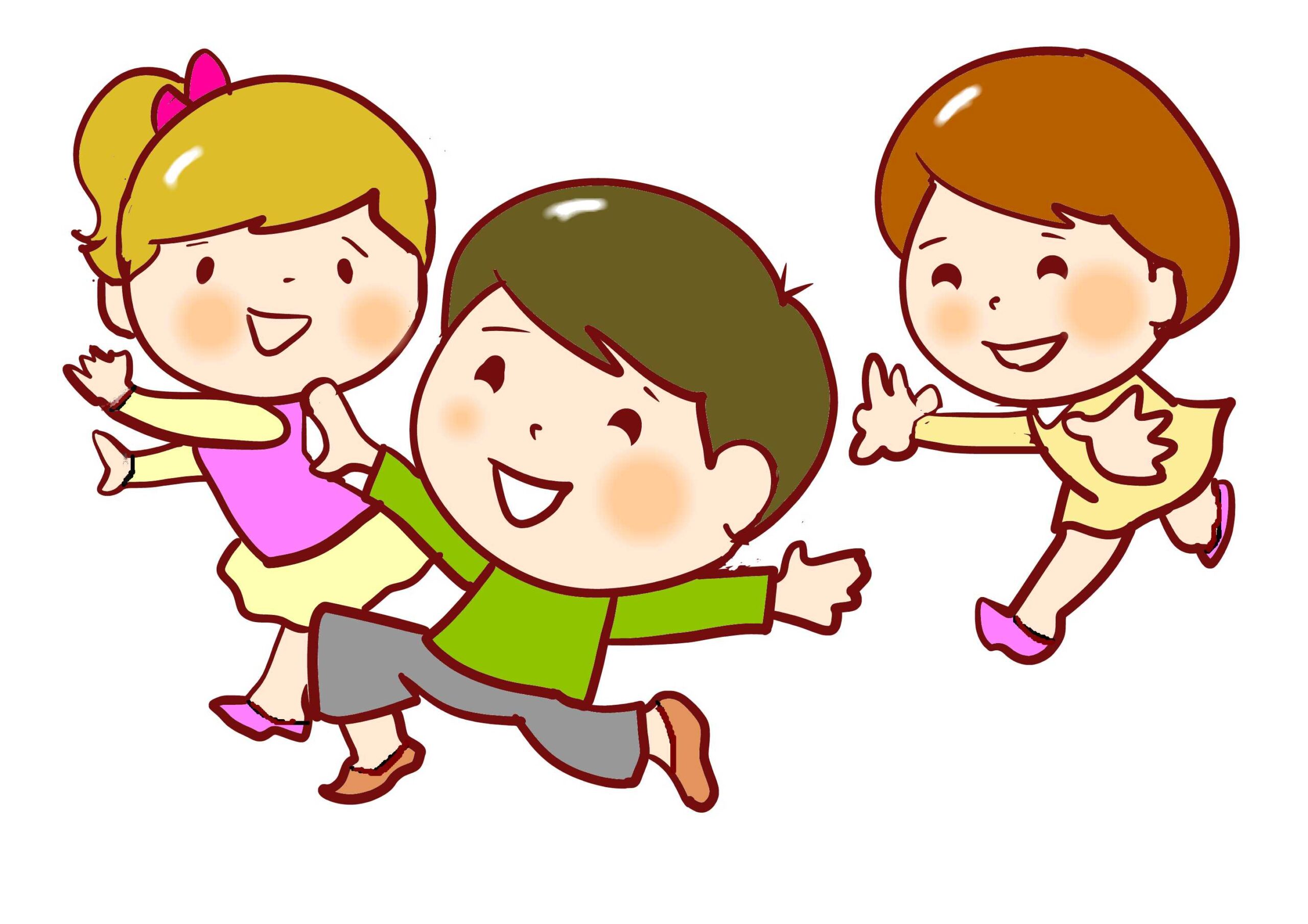鬼ごっこの種類って、どれくらいあるの?」
「保育園でよく遊ばれている定番の鬼ごっこを知りたい!」
そんな保育士さんや子育て中の保護者に向けて、今回は保育園で実際に行われている“鬼ごっこの定番5種”とその特徴、アレンジのコツをご紹介します。
私が保育士として働く中で、子どもの頃に遊んだ鬼ごっこを今の子どもたちが夢中になって楽しんでいるのを見て、とても懐かしい気持ちになりました。そして気づいたのは、「大人になっても鬼ごっこはめちゃくちゃ楽しい!」ということです。
Contents
鬼ごっこの定番① シンプルな「鬼ごっこ」|3歳児からOK
ルールがシンプルな鬼ごっこは、保育園でも最初に取り入れやすい遊びです。
【遊び方】
-
鬼をじゃんけんで決める
-
鬼が「10数える間」に他の子どもたちは逃げる
-
鬼が追いかけてタッチ、最初に捕まった子が次の鬼
3歳児クラスでも遊べますが、人数は5〜6人程度がベスト。あまりに多いと、待ち時間が長くなり、飽きてしまうこともあります。
実際、私が3歳児と遊んでいたとき、最初は4人でスタートしたのに、「仲間に入れて〜!」とどんどん増えて最終的に12人に!楽しそうに「○○ちゃんがオニ〜!」と逃げていたのも束の間、待ち時間に退屈して別の遊びに行ってしまう子も出てきました。
少人数でテンポよく遊ぶことで、鬼ごっこの楽しさがしっかり伝わります。
鬼ごっこの定番② 「色つき鬼」|色を覚え始めた年中〜年長にぴったり
「色つき鬼」や「色鬼」と呼ばれるこの遊びは、色を認識できる年中〜年長児に人気のルールです。
【遊び方】
-
鬼が「赤!」「青!」など色を指定
-
子どもたちは、その色の場所や服に触れればセーフ
-
触れられないまま鬼にタッチされたら交代
園庭にある色だけでなく、保育士や友だちの服・靴の色も対象になるため、観察力や発見力も育まれる遊びです。
ある日、鬼が「むらさきー!」と叫ぶと、園庭にはその色が見当たらず…みんなでキョロキョロ。
すると「先生の靴下に紫があるよー!」と大騒ぎになり、みんなでダッシュ!驚いた先生が思わず逃げだし、笑い声が園庭に響き渡りました。
鬼ごっこの定番③ 「氷鬼」|7〜8人程度で遊ぶと集中できる
氷鬼は、「タッチされたらその場で凍る(動けなくなる)」というルールが特徴の鬼ごっこ。
ルールの理解力と運動能力が必要なので、年長児〜小学校低学年まで幅広く楽しめます。
【遊び方】
-
鬼にタッチされたらその場で静止
-
全員が凍ったら、最初に凍った子が次の鬼
アレンジとして、「まだ捕まっていない子が、凍った子を助けられる」というルールを加えると盛り上がります。助けるためにタッチしようとする子を、反対方向から鬼が狙ってくるスリルは格別!
この遊びは時間をしっかり確保して行うのがポイントです。特に年長児になると、仲間を助けたり協力したりと、集団遊びの楽しさがぐっと深まります。
鬼ごっこの定番④ 「たか鬼」|高低差のある遊びで空間認識力も育つ
「たか鬼」は、高い場所に逃げることで“鬼から逃れられる”というルールの鬼ごっこ。
年中の後半〜年長児になると、地面との高さの違いを理解しながら遊べるようになります。
【遊び方】
-
鬼が「10数える間」に、他の子は高い場所へ逃げる
-
高い場所にいる間はセーフだが、移動時は要注意
高い場所に行きすぎてしまうと危険が伴うため、保育士の見守りが重要です。
実際に遊んでいると、「あぶない!」と注意する子ども、「いまは遊んでるだけだよ!」と応戦する子ども、価値観の違いからちょっとしたトラブルになることもあります。
でもこうした場面こそ、子どもたちが“どう伝えるか”“どう折り合いをつけるか”を学ぶ貴重な機会でもあります。
鬼ごっこの定番⑤ 「かげふみ」|天気のいい日限定の知的遊び
「かげふみ鬼(影踏み)」は、鬼が相手の“影”を踏んだら交代、というユニークな鬼ごっこです。
【おすすめ年齢】年中〜年長
【遊び方】
-
太陽が高く、影がはっきり出る日中に外で行う
-
鬼は影を踏んで、交代
私が「今日はかげふみ鬼をしよう!」と張り切って外に出たところ、雲が出てきて影が消えてしまい、急遽遊びを変更したこともありました。
影が伸びたり消えたりする様子に子どもたちは大興奮。「なんで?」「どうして?」と自然の不思議に触れられる知育要素もあるので、理科的な感性を育てる遊びとしても優秀です。
【番外編】小さな子でも楽しめる歌つき鬼ごっこ
2歳児や、まだルールがうまく理解できない子どもたちには、「むっくりくまさん」や「あぶくたった」など、歌とストーリーがある鬼ごっこがおすすめ。
-
みんなで輪になって歌を歌う
-
ストーリーの展開に合わせて逃げる・追いかける
お兄ちゃん・お姉ちゃんと一緒に遊ぶことで、小さな子も自然とルールを覚えたり、集団の中に入る力が育まれます。
私が子どもの頃は、「小さい子は鬼にならなくていい」という“特別ルール”があり、地域の中で年上の子が年下の子を守る文化がありました。今思い返しても、あたたかく、素敵な思い出です。
【まとめ】鬼ごっこは子どもにとって最高の学びと成長の場
鬼ごっこは、ただ走るだけの遊びではありません。
-
体力や反射神経
-
ルール理解・協調性
-
空間認識や観察力
-
自然現象への興味(影、色など)
遊びながら、子どもたちは驚くほど多くのことを学び取っています。
私自身、大人になって保育士として子どもたちと一緒に鬼ごっこを楽しみながら、遊びには「生きる力を育てる力」が詰まっていると改めて感じました。
道具もお金も要らない“シンプルだけど奥深い”鬼ごっこ。
これからも保育園の定番遊びとして、子どもたちの中で大切に引き継いでいってほしいと心から思います。